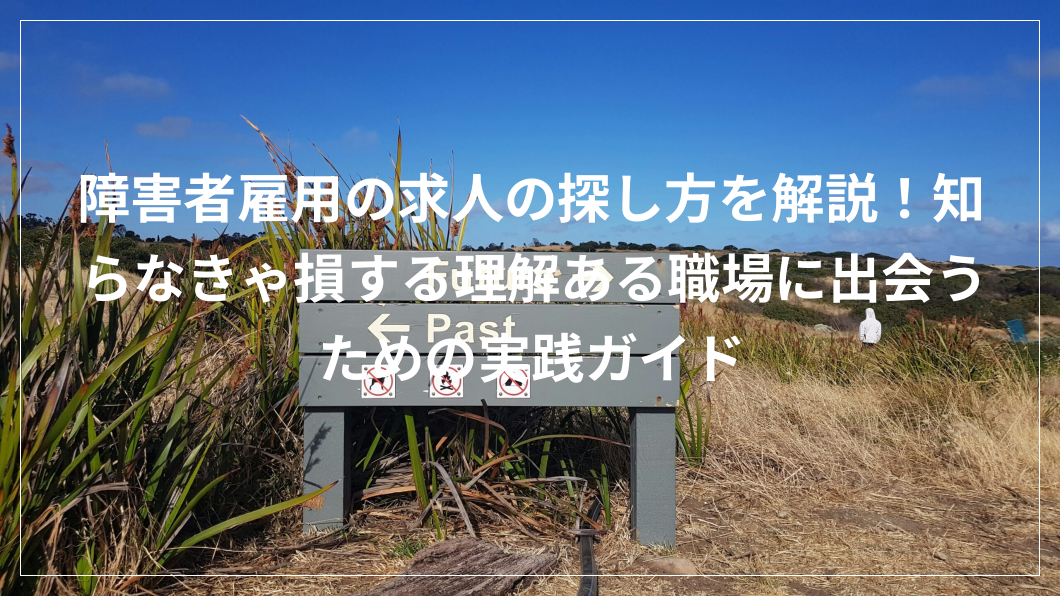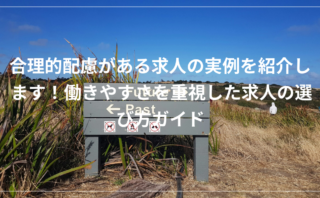この記事では、そんな悩みを抱えるあなたに向けて、障害者雇用の求人の探し方を徹底的に解説します。
「障害者雇用」という働き方に関心があっても、
-
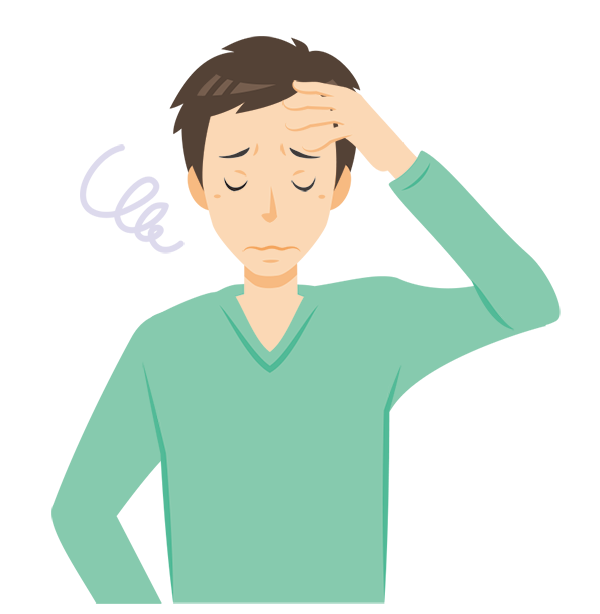
- 「自分に合った求人ってどう探せばいいんだろう?」
- 「理解のある職場って、どう見分ければいいの?」
と疑問や不安を感じている方もいるかもしれません。
知らなきゃ損する、あなたにとって本当に理解のある職場に出会い、安心して長く働き続けるための実践的なガイドです。
ハローワーク、障害者専門の求人サイト、就職エージェントなど、様々な情報源を効果的に活用する方法はもちろん、応募の際の注意点や、面接で自分をしっかりとアピールするためのコツまで、実践的なノウハウを詰め込みました。
ぜひこの記事を参考に、あなたらしい働き方を見つけてください。
障害者雇用で働きたいけど、どこで探せばいいの?
障害者雇用で働きたいと思っても、どこから探し始めたら良いのか悩んでしまうことがあります。
一般的な求人サイトでは自分に合う職場が見つからなかったり、配慮が必要なことをどこまで伝えていいのかわからず不安になることもあります。
ここでは、障害者雇用の基本から、どんな求人があり、どうやって探していくのが安心できるのかをわかりやすく解説していきます。
就労支援サービスや転職エージェントの活用法、職場の見極め方まで、段階を追って紹介しますので、これから仕事を探す方にも役立つ内容です。
障害者雇用ってどんな働き方?普通の求人と何が違うの?
障害者雇用とは、障害のある方が働く際に必要な配慮があらかじめ設けられている働き方のことです。
一般求人とは違い、体調や通院への配慮、業務内容の調整など、無理のない環境で働けるような仕組みが整えられています。
自分の得意分野を活かしやすく、苦手なことには過度な無理をしない働き方が実現できるのが大きな特徴です。
障害者雇用は「配慮」があることが前提の職場
障害者雇用の職場は、働く人の特性に応じた「配慮」が最初から想定されていることが特徴です。例えば、音や光に敏感な方には静かな作業環境が用意されたり、定期的な通院が必要な方には勤務時間を柔軟に調整してくれる職場もあります。こうした配慮の有無は、安心して働き続けられるかどうかに大きく関わってきます。普通の職場では、配慮が必要であることを自ら申告しなければならないケースが多く、精神的な負担になりやすいですが、障害者雇用枠ではあらかじめ配慮が前提となっているため、最初から安心して相談しやすい環境が整っているのが特徴です。
配慮が前提」の職場とは?一般職場との違い
| 項目 | 一般求人 | 障害者雇用枠 |
| 勤務時間 | フルタイム前提が多い | 時短・週3勤務など柔軟に相談可 |
| 仕事内容 | 幅広くマルチタスク要求されがち | 得意な分野を任されることが多い |
| 環境配慮 | 基本的に一般仕様 | 音・光・空間に配慮されている場合も |
| 上司との関係 | 評価・指導が中心 | 定期面談やフォロー制度があることも |
| 配慮の姿勢 | 自己申告が必要なことが多い | 最初から“配慮あり”として設計されている |
障害者雇用の職場と一般求人の職場では、勤務形態や仕事内容、環境面の配慮など、さまざまな点で違いがあります。一般求人ではフルタイム勤務やマルチタスクが求められることが多く、自己申告しないと配慮が受けられないケースが多いです。一方、障害者雇用枠では週3日や短時間勤務も相談しやすく、得意な業務に集中できる体制が整っていることが多いです。環境面でも、照明や音に配慮した作業スペースが確保されていることがあり、定期的な面談やフォロー体制が設けられている職場も少なくありません。
業務内容・勤務時間・通院配慮など、無理のない設計がされている
障害者雇用の職場では、業務内容や勤務時間が無理のないように設計されています。たとえば、短時間から始めて徐々に勤務時間を延ばしたり、通院のある曜日は勤務時間を調整するなど、個々の体調や事情に合わせた働き方が可能です。こうした設計があることで、働きたいという気持ちを無理なく実現することができます。
障害者手帳が必要?応募条件や活用のポイント
障害者雇用枠の求人に応募するには、原則として障害者手帳の所持が必要です。手帳があることで、企業側も必要な配慮を前提とした対応がしやすくなり、応募者自身も特性を伝えやすくなります。手帳がない場合は一般求人が中心となり、配慮が得られにくいこともありますが、手帳を活用することで求人の選択肢が広がり、安心して働ける職場と出会いやすくなります。
障害者手帳を使うとどうなる?応募前に知っておくこと
| 内容 | 手帳なしの場合 | 手帳ありで応募する場合 |
| 求人の選択肢 | 一般求人が中心 | 障害者枠の求人に応募可能 |
| 企業側の理解 | 一般対応。配慮に差がある | 初めから配慮前提のやり取り |
| 面接時の説明 | 配慮をお願いしづらい | 自分の特性を伝える機会がある |
| 書類の通過率 | 条件に合わないと厳しい | 手帳の提示で一定の理解を得やすい |
| 活用のポイント | 無理せず受ける範囲で挑戦 | “配慮されて当たり前”という安心感 |
障害者手帳を活用して応募する場合、求人の選択肢が大きく広がります。企業側もあらかじめ配慮が必要なことを理解しており、面接時にも自分の特性を伝えやすい雰囲気があります。また、応募書類の通過率にも良い影響があり、条件に合う求人であればスムーズに選考が進む可能性もあります。手帳を使うことに不安を感じる方もいますが、“配慮されて当たり前”の環境で働けることは、大きな安心材料になるはずです。
等級や申請状況によって求人の選択肢が変わる場合も
障害者手帳をお持ちの方の就職活動では、手帳の等級や申請状況が応募可能な求人範囲に影響します。企業によっては、特定の等級(例:身体障害者手帳1級〜3級)を応募条件とする場合も。また、就労移行支援事業所や転職エージェントの利用においても、手帳の有無や等級によって受けられるサービス内容やサポート範囲が異なることがあります。特に申請中の方は、手帳交付まで一部支援制度が利用できない場合があるため注意が必要です。
そのため、ご自身の状況に合わせて応募できる求人や利用可能なサービスを事前に確認することが重要です。正確な手帳情報と申請状況を把握し、支援機関と連携しながら進めることで、就労の選択肢が広がり、安心して就職活動を進められます。
障害者雇用の求人ってどこで探せばいい?
障害者雇用の求人を探すとき、どこで探せばよいのか迷う方は多いです。
一般的な求人サイトだけでなく、障害者向けに配慮された支援サービスや、専門のエージェント、就労移行支援などを活用することで、自分に合った職場を見つけやすくなります。
就労移行支援を利用して、プロと一緒に探す
就労移行支援は、障害を持つ方が安定して働くためのサポートを受けられる福祉サービスです。 面談・登録では、利用者の不安や希望を丁寧に聞き取り、気持ちが整理される体験が得られます。
就労移行支援を使った就活の流れと得られたこと
| ステップ | 内容 | 利用者の声 | 支援の効果 |
| 1.面談・登録 | 不安や希望をヒアリング | 「話すだけで気持ちが整理された」 | 自分の課題・強みが言語化できる |
| 2.通所開始 | 生活リズムやビジネスマナーの訓練 | 「毎日通う習慣がついた」 | 継続する力と自信がつく |
| 3.職場体験 | 実際の仕事を“試す”機会 | 「働けそうなイメージが湧いた」 | 働く前の“不安”が“実感”に変わる |
| 4.就職サポート | 面接練習・求人紹介・同行支援など | 「一人じゃ無理だったと思う」 | 実際の就職率が高い理由はここ |
通所開始後は、ビジネスマナーや生活リズムを整える訓練を通して、自信と継続力が育まれます。
職場体験を通じては、実際に働くイメージを持つことができ、不安が減ります。
そして、面接練習や求人紹介、同行支援を含む就職サポートが実を結び、就職成功へとつながるのです。
“見つける”だけじゃなく“続けられる”職場を一緒に考えてくれる
就労移行支援では、ただ求人を紹介するだけでなく、その人が長く安心して働き続けられる職場かどうかを一緒に考えてくれます。
障害特性や配慮が必要な点を考慮しながら、継続可能な職場環境を探す姿勢があるため、定着率の高さにもつながっています。
相談しながら就職先を選べることが心強いです。
転職エージェントで非公開求人にアクセスする
転職エージェントを利用することで、障害者雇用に配慮された非公開求人にアクセスすることができます。
障害者特化型エージェントのサービス比較
| サービス名 | 特徴 | 向いている人 | 利用者の声 |
| atGP | 配慮条件を丁寧にヒアリングし、求人を紹介 | 手厚いフォローを希望する人 | 「面接同行が安心できた」 |
| dodaチャレンジ | 精神・発達障害など幅広い対応実績あり | 大手企業を目指したい人 | 「求人の質が高かった」 |
| ランスタッド障害者支援 | 外資系・高年収求人あり | スキルを活かしたい人 | 「キャリア相談が役立った」 |
→ランスタッド アフィリリンクを貼る
atGPやdodaチャレンジなど、障害者特化型のサービスが多数
関連ページはこちら:「dodaチャレンジ 口コミ」へ内部リンク
→ 障害別専門支援の就労移行支援サービス【atGPジョブトレ】
関連ページはこちら:「atGPジョブトレ 口コミ」へ内部リンク
ハローワークの専門窓口を活用する方法
ハローワークには、障害者専用の相談窓口があります。
予約なしで訪問することも可能ですが、事前に電話するとよりスムーズです。
ハローワークの専門窓口を活用する際のポイント
| 利用ステップ | 内容 | 知っておくべきこと | よくある疑問への答え |
| 窓口訪問 | 障害者専用窓口で受付 | 地域によって対応に差あり | 「予約なしでも行ける?」→OKだが事前電話が◎ |
| 面談 | 希望条件や障害の状況をヒアリング | 就労支援員がつく場合も | 「通院や配慮は話していい?」→話すことで合う求人に出会える |
| 求人検索 | 専用端末で検索可 | “非公開求人”がある場合も | 「ネットに出てない求人って?」→窓口だけの案件も多い |
| 職場見学・紹介 | 必要に応じて実施 | ハロワが橋渡しをしてくれる | 「職場見学はお願いできる?」→可能。積極的に相談を |
面談では希望や体調、通院状況などを話すことで、合った求人を紹介してもらいやすくなります。
検索端末には一般に出ていない求人も掲載されており、思わぬ出会いがあるかもしれません。
職場見学なども相談できるので、積極的に支援員にお願いしてみましょう。
地域に根ざした求人や助成制度についても相談できる
ハローワークでは、地域密着型の求人情報を持っていたり、助成金や制度に関する情報も得られたりします。
地元での就職を考えている方や、各自治体独自の支援を活用したい方には特におすすめです。
制度に詳しい職員に相談することで、自分に合った選択肢が見つかる可能性が高まります。
障害者雇用の求人票ではわからない“職場の雰囲気”の見極め方
求人票には書かれていないけれど、実際に働く上でとても大切なのが「職場の雰囲気」です。
どんなに条件が良くても、環境や人間関係にストレスを感じてしまうと長く続けるのは難しいものです。
ここでは、職場見学や面接の場面で、どんなポイントをチェックすれば安心して働ける職場に出会えるのかを、具体的にご紹介していきます。
職場見学でチェックしたいポイント
職場見学は、求人票だけでは見えてこない職場の空気や人間関係を知るための絶好のチャンスです。実際に足を運んでみることで、スタッフ同士のやり取りや、働く人の表情、オフィスの音や照明の雰囲気など、さまざまなことが見えてきます。たとえば、挨拶が自然に交わされているか、職場の空気がピリピリしていないかといった点は、長く働けるかどうかの判断材料になります。また、作業スペースの広さや座席の配置など、自分にとって快適に感じられる環境かどうかも見ておきたいポイントです。実際にその場の雰囲気を体感することで、「ここなら安心して働けそう」と思える職場に出会える可能性が高まります。
職場見学でチェックしておきたい観察ポイント一覧
| 観察する要素 | チェックポイント | 理想的な例 | 避けたい例 |
| 職場の雰囲気 | 挨拶・表情・空気感 | 穏やかで挨拶が交わされている | ピリピリして無言の空気 |
| 環境の音や光 | 雑音の有無・照明の種類 | 静か/自然光・間接照明あり | 大音量の電話・蛍光灯まぶしい |
| 作業スペース | 自分の空間があるか | デスクが整っていて距離感も適度 | 密集していて落ち着かない |
| 上司・同僚の様子 | 接し方や声かけのトーン | 丁寧でゆるやかなコミュニケーション | 命令口調・圧が強い |
職場見学では、求人票や面接だけではわからない職場の雰囲気を感じ取ることができます。まず注目したいのは、職員同士のコミュニケーションです。挨拶が自然に行われていたり、話し方が丁寧で落ち着いている職場は、安心して働ける可能性が高いです。また、スタッフの表情や、利用者への声かけの様子も見ておくと良いでしょう。さらに、室内の照明や音の環境も重要なポイントです。まぶしすぎる蛍光灯や騒がしい機械音があると、集中しにくかったり、ストレスの原因になることもあります。座席の間隔や作業スペースの広さ、休憩スペースの雰囲気など、自分がリラックスできるかどうかも大切な判断材料です。このように、五感を使って観察することで、自分に合った環境かどうかが自然と見えてきます。
作業環境・人の対応・音や照明など、五感で感じる情報を大事に
求人票には書かれていないけれど、実際に働くうえでとても大切なのが「職場の雰囲気」です。その雰囲気を知るには、五感を使った観察が欠かせません。たとえば、職場の空気が張り詰めていないか、穏やかな声かけがされているか、誰かが困っているときに自然に声をかけ合える雰囲気か、といった点を見てみましょう。また、照明の明るさや種類、周囲の音の大きさも要チェックです。自分にとってまぶしすぎたり、音が気になるような環境では、集中力が続かないこともあります。さらに、スタッフや他の利用者との距離感が近すぎないか、自分のペースで動けそうかどうかも大切なポイントです。自分の感覚で「ここなら落ち着いて働けそう」と思えるかどうかを、実際の空間で確かめておくと安心です。
面接時に確認すべき「合理的配慮」の具体例
| 必要な配慮の例 | 面接での聞き方 | 意図 | 確認すべきポイント |
| 通院への配慮 | 「定期的な通院があるのですが、柔軟に対応いただけるでしょうか?」 | 勤務調整が可能かどうか | 有休/中抜け対応など |
| 音・光などの環境面 | 「集中力に影響が出やすいため、席の場所などご配慮いただけることはありますか?」 | 作業環境の調整可否 | 静かなスペースが確保できるか |
| 休憩の取り方 | 「体調により、タイミングを見て休憩を取りたいのですが可能ですか?」 | 自律的な調整が許されるか | 一律ルールでないか確認 |
求人に応募する際、面接の場では「自分に必要な配慮が受けられるか」を確認することがとても大切です。合理的配慮とは、障害のある方が安心して働けるように、企業側が環境を調整することを意味します。たとえば、体調に波がある方であれば「休憩の時間や取り方に柔軟性がありますか?」といった質問が有効です。また、感覚過敏がある場合には「静かな席での作業が可能ですか?」といった具体的な要望を伝えておくと、ミスマッチを防ぐことができます。通院が必要な方は、「定期的に通院の時間を確保したいのですが、勤務時間の調整は可能でしょうか?」と確認してみましょう。こうした質問を通じて、職場の受け入れ体制や柔軟な姿勢を知ることができ、安心して働き始めるための準備になります。
自分に必要な配慮が“想定されているか”がカギになる
面接の場では、自分にとって必要な配慮がその職場であらかじめ想定されているかどうかを確認することが重要です。想定されている職場では、面接官のほうから「何か必要な配慮はありますか?」と聞いてくれることも多く、障害に対して理解がある姿勢が感じられます。逆にそのような問いかけが一切なく、配慮に関する質問に対しても戸惑った反応がある場合は、受け入れ体制が十分でない可能性があります。たとえば、「通院のために週に一度、午前中の勤務時間を調整したい」といった希望を伝えたときに、すぐに対応例を挙げてくれるかどうかが判断のポイントになります。職場がすでに障害者雇用の経験を積んでいる場合、具体的な対応策がすぐに提示されることが多く、自分が無理なく働ける環境が整っている可能性が高いです。面接では、こうしたやりとりの中から、配慮がどこまで具体的に想定されているかを見極めていくことが大切です。
障害者雇用の求人探しのときに大切にしたい“自分軸”のつくり方
求人を探すとき、つい条件や待遇ばかりに目がいきがちですが、本当に大切なのは「自分がどんな働き方をしたいか」をはっきりさせることです。自分の希望や価値観を軸にすることで、迷わずに求人を選べるようになり、長く安心して働ける職場とも出会いやすくなります。
働きたい理由を明確にする
求人探しを始める前に、自分が「なぜ働きたいのか」という理由を言葉にしてみることが大切です。生活のため、社会とのつながりを持ちたい、自分の力を活かしたいなど、人それぞれの動機があります。明確な理由があると、求人を選ぶ際の基準がはっきりし、迷いや不安も少なくなります。たとえば「人と関わる仕事がしたい」と思えば、接客や支援業務に向いているかもしれませんし、「集中して一人で取り組みたい」という人は事務や軽作業が合うかもしれません。自分の内側にある働く目的を見つめ直すことで、応募先を選ぶときに納得感を持って決断できるようになります。
働きたい理由を明確にするための内省ステップ
| ステップ | 質問例 | 自分の答え | 気づいたこと |
| ステップ1 | 「今までどんな仕事が楽しかった?」 | 人と話を聞く仕事が楽しかった | 自分は“聞き役”にやりがいを感じる |
| ステップ2 | 「辞めたいと思ったのはどんな時?」 | 評価されないとき、無理を強いられたとき | “感謝される”職場を求めている |
| ステップ3 | 「働くことで何を得たい?」 | 社会とのつながり/生活リズム/自己肯定感 | お金だけじゃない“居場所”がほしい |
働く理由をはっきりさせるためには、自分の気持ちを丁寧に振り返る内省の時間が必要です。まずは「なぜ今、働きたいと思ったのか」を紙に書き出してみることから始めてみましょう。収入を得たい、生活リズムを整えたい、社会とのつながりを持ちたいなど、出てきた理由に対して「なぜそれが自分にとって大切なのか」と問いかけを繰り返していくと、より深い動機に気づくことができます。さらに、過去にやって楽しかったことや、反対に辛かった経験を振り返ることで、自分にとって心地よい働き方のヒントが得られます。こうした内省のプロセスを通して、自分にとっての“働く意味”が少しずつ形になっていくはずです。
お金のためだけじゃない、「居場所としての職場」があるか
働く理由としてお金は大切ですが、それだけでは長く続けるのが難しくなることもあります。安心して過ごせる空間や、誰かと関わりながら日々を重ねられる場として、「居場所」と感じられる職場があるかはとても重要です。たとえば、同じような悩みを持つ人が働いていたり、気軽に話しかけられる雰囲気があったりすると、自然と気持ちが楽になります。また、自分を否定されない空気感や、ちょっとした体調変化に気づいてくれる人がいるだけでも、働くことが心強く感じられるようになります。職場は単なる労働の場ではなく、自分らしさを保ちながら社会とつながる場所でもあるのです。
希望条件を細かく書き出して優先順位をつける
自分にとって大事な条件を整理するには、まずは思いつくままに希望を書き出してみることが大切です。たとえば「短時間勤務がいい」「自宅から通いやすい」「人との会話が少なめ」「PC業務が中心」など、具体的に書き出すことで頭の中が整理されていきます。次に、それらを「絶対にゆずれない条件」「できればかなえたい条件」「妥協してもよい条件」の3つに分けてみましょう。そうすることで、求人を比較する際に何を基準に判断すればよいかが明確になります。このシートを作っておくと、就労支援員や面接担当者に自分の希望を伝えるときにも役立ちます。
希望条件を整理するための優先順位付けシート
| 条件 | 自分の希望 | 優先度(高・中・低) | 理由 |
| 勤務時間 | 週3〜4、1日5時間以内 | 高 | 体調に波があるため |
| 通院対応 | 週1の午前中に通院 | 高 | 治療継続が就業の前提 |
| 在宅勤務 | 可能なら週の半分在宅 | 中 | 通勤の負荷を減らしたい |
| 職場の人間関係 | 穏やかな雰囲気 | 高 | 過去の職場でのトラウマがある |
| 給与水準 | 月10万円以上 | 中 | 生活に必要な最低ライン |
「在宅希望」「通院配慮」「静かな環境」など正直に洗い出す
希望条件を洗い出すときは、「こんなこと言ってもいいのかな」と遠慮せずに、自分の気持ちに正直になることが大切です。「在宅勤務ができると安心」「週1回の通院に配慮してほしい」「騒がしい場所が苦手で静かな環境が合っている」など、具体的な希望を一つずつ言葉にしてみましょう。最初から完璧に整理する必要はなく、あとから見直しながらでも大丈夫です。自分の特性や体調、生活リズムを考慮して「こういう職場なら働けそう」と思える条件を見つけていくことで、自分軸が育っていきます。自分にとって無理のない働き方を知ることが、職場探しの第一歩になります。
不安や希望を“言葉にして相談する”習慣を持つ
自分の気持ちを相手に伝えるのが苦手な方は多いですが、「不安」や「希望」を言葉にすることは、安心して働くための大切なスキルです。まずは簡単な訓練として、「今日不安に思ったこと」「こうなったらいいなと思うこと」を毎日ノートに書いてみることから始めましょう。次に、それを第三者に伝える練習として、支援員や家族など身近な人に話してみるのも効果的です。相談することに慣れてくると、面接や職場でのやりとりでも自信を持って伝えられるようになります。言葉にしてみることで、自分の気持ちが整理され、相手に伝わる内容も自然と明確になっていくものです。
不安や希望を“言葉にして相談”できるようになる訓練シート
| 状況 | 書き出した不安・希望 | 言葉にした例 | 相手に伝えた結果 | 感じた変化 |
| 通院について | 「通院があるのに迷惑かも…」 | 「週1で通院があり、その日は午前勤務希望です」 | 「調整できますよ」と言ってもらえた | 言ってよかったと安心 |
| 業務負荷 | 「いきなりフルタイムは無理かも」 | 「最初は短時間勤務から始めたいです」 | ペースを考慮したプランを提示された | 自分の希望が通じたことで前向きに |
| 対人ストレス | 「会話が続かないのが不安」 | 「会議や雑談は控えめだとありがたいです」 | 配慮できるよう調整すると回答あり | 無理せず働ける職場かもと感じた |
それが“配慮のある職場”と出会う第一歩になる
自分の思いや希望を言葉にできるようになると、それに応えてくれる職場と出会いやすくなります。たとえば「集中できる環境が必要です」と伝えれば、静かなスペースを用意してくれる職場が見つかるかもしれません。逆に、言葉にしなければ相手は気づくことができず、働きにくさを感じてしまう可能性があります。だからこそ、ちょっとしたことでも相談する習慣を持つことが大切です。丁寧に耳を傾けてくれる企業は、配慮のある環境づくりにも前向きな傾向があります。自分のことを正直に伝えることが、長く安心して働ける職場との出会いにつながっていくのです。
障害者雇用の求人の探し方のまとめ
この記事では、障害者雇用の求人の探し方を解説などについて紹介しました。
障害者雇用の求人を探すときには、単に条件に合うかどうかだけではなく、自分にとって働きやすい環境や、安心して過ごせる「居場所」としての職場であるかを大切にすることがポイントです。
そのためには、まず「なぜ働きたいのか」という気持ちを見つめ直し、希望や不安を丁寧に言葉にすることから始めましょう。
通勤や業務内容、周囲とのコミュニケーションの取りやすさなど、自分にとっての優先事項を明確にし、支援者や企業としっかり共有することが、ミスマッチのない就職につながります。
焦らずに一歩ずつ進んでいけば、自分に合った職場はきっと見つかるはずです。
【おすすめ記事】
こちらの記事も役立つのでぜひ読んでみてください。
配慮されている求人ってどんなもの?
実際の「合理的配慮」がある求人事例を紹介し、どんな働き方が可能か具体的に解説しています。
→ 合理的配慮がある求人の実例を紹介します!働きやすさを重視した求人の選び方ガイド
障害者手帳を転職活動に活かすには?
転職時の使い方や、企業への伝え方のコツを紹介しています。
→ 障害者手帳を活用した転職成功ガイド!就職支援で面接対策・書類も万全
うつ病からの転職成功体験談
「もう働けないかも」と思った人が見つけた働き方と、安心できる職場との出会いを紹介しています。
→関連ページはこちら「うつ病 転職 体験談」へ内部リンク
就労移行支援ってどう使うの?
初めての利用でも安心できる、手続きから通所、就職までの流れをわかりやすくまとめています。
→関連ページはこちら「就労移行支援 利用 方法」へ内部リンク
トップページに戻る
→ キャリア・ログポース
さまざまな転職サービスを比較してみたい方へ
他のおすすめ転職サービスを見てみたい方へ
厚生労働省「障害者雇用対策」も参考になります。